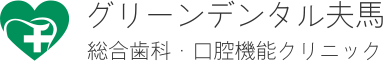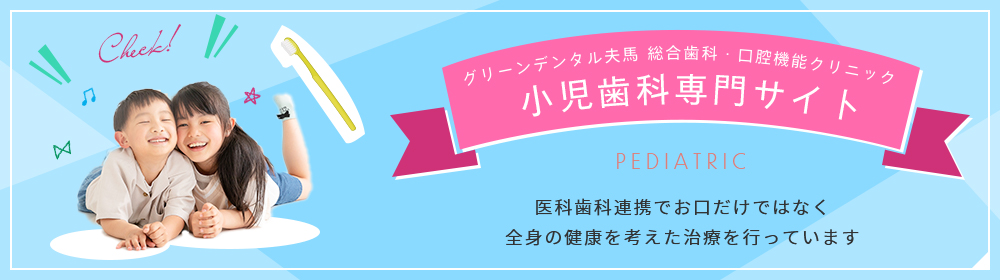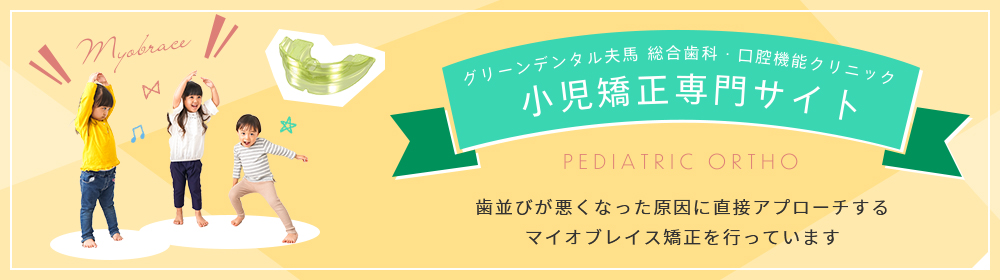子どもの「いびき」や「口呼吸」が気になっていませんか?
子どもの口呼吸は、歯並びを悪くする原因のひとつと言われています。
また、いびきはそれ自体が歯並びに直接的な悪影響を及ぼすものではありませんが、お口周りの筋肉や機能に何らかの異常が起こっているかもしれません。
こうした子どもの口呼吸やいびきを根本から改善する方法に「ORT(オルト)矯正」があります。ただし、さまざまなメリットがある反面、いくつかのデメリットがある点に注意が必要です。
今回はそんなORT矯正の注意点に焦点を当てて詳しく解説をします。
目次
■ORT矯正のデメリットとは?
マウスピース型の矯正装置を装着して、口呼吸や口腔周囲筋の使い方を改善するORT矯正。
以前のコラム「子供の間違った食べ方や飲み込みのクセを改善!ORT矯正のメリット」で紹介した通り、外で装着する必要がない、食事や歯みがきを普段通りに行える、治療に伴う痛みが少ないなど、たくさんのメリットがあるのですが、同時に以下のようなデメリットも正しく理解しておくことが大切です。
【デメリット1】お子様のモチベーションが必要
ORT矯正の大きなメリットは「好きなときに取り外せる」ことです。外にお出かけしたときや学校にいるときなどは、矯正装置を使用する必要がありません。
そうなると家に帰ってからも「つけなくていいじゃん」と億劫になるお子様も、実は少なくないのです。ORT矯正のマウスピースは、矯正に伴う痛みも少ないことから、比較的続けやすい矯正治療です。
しかし、お子様がその必要性を理解できておらず、「飽きた」「つけたくない」と嫌がってしまうことも。つまり、お子様のORT矯正へのモチベーション次第で治療結果や進行が大きく変わることもあるのです。
【デメリット2】親御様によるサポートが不可欠
ORT矯正は、低年齢から始める矯正治療のため、お子様だけでモチベーションを維持するのは困難です。親御様がきめ細かくサポートすることで初めてORT矯正の継続や成功につながるため、その点は十分な注意が必要です。
【デメリット3】毎日装着しなければ効果が得られない
ORT矯正のマウスピースは、日中の1時間と就寝中に装着する必要があります。
このルールを守れないと、適切な矯正効果が得られません。ORT矯正にかかる期間は1~3年程度で少し長く感じるかもしれませんが、マウスピースの装着は習慣化することで、つけ忘れや装着時間の不足を回避しやすくなります。
※期間はお子様の状態によって異なります。
【デメリット4】費用が高くなることがある
ORT矯正は、歯並びを悪くした原因を根本から取り除く矯正治療で、将来的に抜歯を回避したり、顔つきが健やか育ったりするなどのメリットが得られる反面、自費診療となるためむし歯治療などに比べると費用が高くなります。
【デメリット5】年齢によってはORT矯正ではない治療法をご提案することも
ORT矯正は、始める年齢やタイミングが大切です。当院のORT矯正は5~6歳から始めることができ、受診した年齢や症状によってはそれ以外の方法を提案させていただくこともあります。
■子どものいびきや口呼吸はORT矯正で治る?
子どものいびきや口呼吸の原因は、お口の中にあることが多いです。
例えばいびきであれば、下顎の発育が遅れていたり、歯列が狭くなっていたりすると、舌が奥に落ち込む「舌根沈下」が起こりやすくなり、気道が狭くなることでいびきを誘発しやすくなっています。
口呼吸も同様に骨格や歯並びが関係している面もあれば、舌の位置や口腔周囲筋の使い方が原因となっているケースもあります。さらに、猫背などの悪い姿勢が続くと、顎や舌の位置に影響し、気道が狭くなることで呼吸がしづらくなり、いびきや口呼吸を助長してしまうこともあります。
こうした問題には、舌の位置や口腔周囲筋の使い方を見直し、姿勢にもアプローチできるORT矯正で改善が期待できます。
■まとめ
今回は、子どものいびきや口呼吸を改善できるORT矯正のデメリット・注意点について解説しましました。
ORT矯正には、お子様の矯正治療へのモチベーション、親御様によるサポート、毎日のそ装着、などのデメリットがありますが、お子様のお口の癖を根本的に改善できるメリットの多い治療法でもあります。
江南市小郷町のグリーンデンタル夫馬の無料相談では、こうしたORT矯正の注意点まで詳しくご案内しております。その他にもORT矯正に関する疑問や不安があれば、何でもお尋ねください。